
1978 年生まれ、慶応義塾大学 医学部教授
専門はデータサイエンス、科学方法論、Value Co-Creation
データサイエンスなどの科学を駆使して社会変革に挑戦し、現実をより良くするための貢献を軸に研究活動を行う。専門医制度と連携し 5000 病院が参加する National Clinical Databaseや、LINE と厚労省の新型コロナ全国調査、その他医学領域にとどまらない様々な実践に取り組む。それと同時に、アカデミアだけでなく、行政や経済団体、NPO、企業など様々なステークホルダーと連携して、新しい社会ビジョンを描く。宮田が共創する社会ビジョンの 1 つは、いのちを響き合わせて多様な社会を創り、その世界を共に体験する中で一人ひとりが輝くという“共鳴する社会”である。
2003 年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士(論文) 早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科 医療品質評価学講座助教を経て、2009 年 4 月東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座 准教授、2014 年 4 月同教授(2015 年 5 月より非常勤 、2015 年 5 月より慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 教授。2020年12月大阪大学 招へい教授就任。
大阪・関西万博の静けさの森とシグネチャーパビリオンBetter Co-Beingは、人と世界、そして未来を結ぶ多層的な共鳴の実験場です。デジタル技術による分断や監視の危うさと、短期利益追及による自然環境の破壊や資源枯渇という現実は、もはや避けては通れない課題となりました。しかし、ここではそれらの危機を直視したうえで、多様な価値観とテクノロジー、そして森に象徴される自然や生態系と響き合う道筋を提示します。移植を経て再生する木々や、キャノピーを通して見上げる空が映し出す虹の儚い瞬間は、世界との共創がいかに繊細でありながらも力強いかを物語ります。
パビリオンの作品群と空間体験が描くのは、デジタル革命を経て生まれる新しいつながりと共鳴の可能性です。声を重ね、互いの違いを認め合い、意思を紡ぐことで、未来への新たな道筋が開かれます。共に空を見上げ、目には映らない多様な結びつきを共有することで、人は自らの立ち位置を見出し、社会の在り方を問い直す契機を得ます。そして、かけがえのない瞬間の共鳴こそが、より良い未来を切り拓く原動力となるのです。私たちはこの場を後にするすべての来訪者がその共鳴を胸に刻み、日々の営みへとつなげていくことを願っています。
宮田裕章
いまや世界は、「未来への警鐘」と「分断された価値観」がせめぎ合う時代を迎えている。気候変動など地球規模の危機は、大量生産・大量消費社会のひずみを浮き彫りにしながら、人々の意識と行動に変革を迫ってきた。一方、デジタル技術の急速な発展とグローバルな接続が、新たな共創の可能性を示す一方で、エコーチャンバーによる分断を生む負の側面を生み出しているのも事実である。こうした両義的な力が交錯する中、大阪・関西万博の中心に据えられる「静けさの森」は、自然と人工物がいかに共在し得るかを問いつつ、万博という舞台で未来へのつながりを共創する場として構想された。
静けさの森では、多様ないのちが響き合う象徴として、木々を中心とする生態系が描かれている。万博の中心部に広がるこの森は、人工物だけに頼るのではなく、長い年月をかけて築かれてきた自然の循環と共存する未来を投射するものだ。森の中で日照が取れず枯れていく運命にある木々の移植により、新たな生態系を再生する過程自体が未来への歩み示している。静けさの森と一体となってリングの中央部に佇むシグネチャーパビリオンBetter Co-Beingは、そうしたいのちへの問いを深め、未来への共鳴を描く試みでもある。
情報革命そしてそれに続くデジタル革命によるインターネットやSNS、生成AIといった技術革新は、人間の暮らしを根底から変えた。一方、監視資本主義やアルゴリズムによる格差拡大、プライバシー侵害など、負の側面も急速に拡大している。デジタル技術は人間の可能性を広げる一方で、深刻な分断と人権制限の手段にもなり得る存在である。しかし、そのような課題を直視した先にこそ、デジタル技術による真の価値創造の可能性があると考える。データの共有や多様なつながりの可視化は、人と人、社会と自然、現在と未来をつなぐ新たな回路を築きうる。
シグネチャーパビリオンBetter Co-Beingでは、こうしたリスクを踏まえたうえで、デジタル技術を「共鳴」の力へと転じ、未来へと続く価値創造の基盤として再定義したい。ここでいう共鳴とは、単なる可視化や情報交換の域を超え、互いの行動や意志が折り重なることで新たな社会像を形作っていくプロセスを指す。監視や統制の道具としてではなく、人間を主体的に多様な可能性に接続し、未来を共創する力へと昇華する——それこそが、デジタル革命の本質であると考えている。
最終的に本パビリオンで提示するのは、具象的な未来の姿ではない。未来には多様な可能性があり、理想とする姿は時代や環境によっても異なってくる。また、もちろん未来への軸は2025年の大阪・関西万博で芽生えたものだけでなく、今後も変化していくだろう。一方で、どのように自分自身や他者の大切なものと向き合い、世界とつながりながらも未来へと向かうのか? こうした問いは、様々な時代の中において、人類の活動においても普遍的に紡がれてきた。テーマ事業「いのちを響き合わせる」はそうした問いと向き合い、デジタル技術の発展を通じて新たに顕在となりうる「共鳴の中で未来へと向かうあり方」について、静けさの森、そしてシグネチャーパビリオンBetter Co-Beingで紡がれる体験を通して、問いを立てるものである。
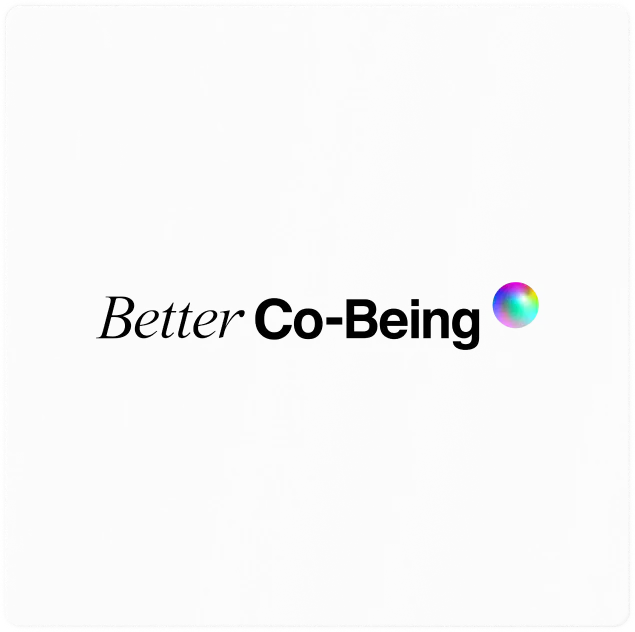
パビリオンの名称「Better Co-Being」は、つながりのなかで共に生きる「未来への共鳴」を意味する。デジタルによってつながりが可視化され、サステナビリティという概念が個々人の行動に強い影響力を持つようになった。一方で、デジタルは一人ひとりに寄り添うツールとしても力を発揮する。一人ひとりの多様な豊かさと、未来への持続可能性の間で調和を取りながら歩み、共に考えるものの見方を「Better Co-Being」と呼ぶ。
Co-beingに近い概念の言葉はいくつもある。例えば、becomingという言葉を挙げると、まだ至っていないとも捉えられ、現在を否定するニュアンス含む。また、Convivialityなら楽しむという意味で、そうした機構を持たない植物や生物はco-beingから除外することになる。Co-existenceは生物学的な観点からの生存の両立といいう観点からより狭義な意味となる。一方、beingという規定を使うことにより、現在を否定しない。さらに、Co-が付くことで、生命でない無機物や、植物、地球環境も対象としながら、つながり、未来へと向かうという観念を包含する。
社会には格差や抑圧といった構造的問題なお深く巣くう、自然環境の破壊や資源の枯渇も深刻化している。しかし、一人ひとりが持つ多様な価値観と、その調和の中で未来をより開く方策を探ることは、もはや不可避の課題である。Better Co-Beingは、その歩みを示す問いかけである。